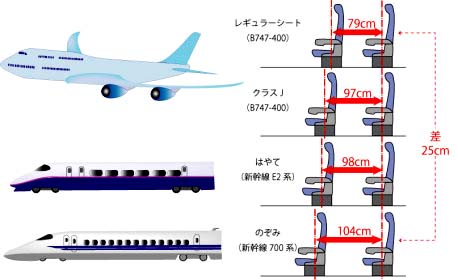路線・軌道設備
-

路線は、在来線と別ルートで新規に建設した線路設備を用いる(ミニ新幹線を除く)。
軌間は標準軌 (1,435mm) を用いる。
カーブにおける曲率半径を大きくし、できる限り直線を確保する。
曲率半径は東海道新幹線が2,500m(制限速度255km/h、N700系のみ制限速度270km/h)、山陽新幹線以降に建設された各線は4,000m以上(現状の最高速度300km/hでは減速せず通過できる)が基本となっている。
但し、東海道新幹線の東京 - 新横浜間や東北新幹線の東京 - 大宮間のような都心部区間、あるいは全列車が停車する主要駅の前後においては、その限りではない。
また、通過列車が多い熱海駅や徳山駅の前後などにおいても、用地や地形の関係からやむを得ず急曲線が存在する区間がある。
事故防止のため以下の設計を行う。
自動車との衝突事故を防ぐため、踏切を一切設けない(ミニ新幹線として運行されている在来線の場合は、踏切数を削減すると共に保安設備を強化している)。
線路内に一般の人が立ち入れない様にする。
前項も含めた対策として全線立体交差とする(ミニ新幹線を除く)。
また、列車の運行妨害等に対しては法律面でも「新幹線特例法」によって在来線より厳しい罰則を定めている。
通過列車との接触など人身事故を防ぐため、プラットホームに可動ゲート付きの安全柵を設ける(例:新横浜駅や新神戸駅など)か、通過線と待避線を分ける(例:静岡駅、福島駅など)。
ただし、大宮駅や軽井沢駅など通過列車の通過速度が低い駅には安全柵のみ設けられている。
また、東海道新幹線・山陽新幹線の東京駅や名古屋駅、京都駅、新大阪駅、博多駅など全列車が停車する駅には、当初柵などは設けられてはいなかったが後に安全柵のみが設けられた。
また、東海道新幹線では、静岡駅や浜松駅など、通過線と待避線が分かれていながら安全柵が設置されている駅もある。
乗り心地や安全性の向上、騒音対策などから、レールや分岐器(ポイント)にも様々な工夫が施されている。
レールは、継ぎ目の数を減らしたロングレールを使用。
東北新幹線のいわて沼宮内駅 - 八戸駅間には、国内最長の延長約60.4kmに亘る「スーパーロングレール」が用いられている。
ポイントは、通過時の振動が少ない弾性分岐器と、レール交差部の欠線部を埋めるノーズ可動クロッシングを使用。
また、高崎駅北方にある上越新幹線と北陸新幹線(長野新幹線)との分岐には、分岐側が160km/hで通過できる国内最高水準かつ最長のポイントが設置されている。
新幹線の駅間距離は、中距離・長距離輸送を主とすることから、原則として在来線より長く取られている(30 - 40km程度)。
信号システム
-

地上の信号機を車上から目視確認して運転する事は高速運転のため不可能であり、自動列車制御装置 (ATC) を備え、運転室内に車内信号による運行指示が表示される。
運転指令所の列車集中制御装置 (CTC) から、全ての列車の運行状況を一括管理している。
現在では列車運行管理システム (PTC) も導入されており、通常のポイント操作や信号制御、駅自動放送から車両の管理整備、輸送障害時の復旧ダイヤの作成に至るまで、あらゆる業務がコンピュータによって高度にシステム化されている。
電源方式
-
単相交流25,000Vで電力を供給する。
饋電(きでん)方式は現在ではAT方式に統一された(当初、東海道新幹線はBT方式)。
電源周波数は以下の通り。
東海道新幹線では60Hzに統一して給電している。
静岡県の富士川を境に50Hzと60Hzの電源周波数区分を跨っているが、当初から山陽方面への延長を構想していたため全線で統一し、車両側の特高圧機器の簡素化を図ったもの。
なお、電源周波数区分50Hzの地域では周波数変換所が設けられ、新幹線電源用に60Hzに変換している。
北陸新幹線(長野新幹線)は軽井沢駅 - 佐久平駅間で50/60Hzの切り替えセクションが存在する。
車両側も50/60Hzの双方に対応。
上記以外の山陽(東海道新幹線を延長した形で建設された)・東北・上越・九州(鹿児島ルート)の各新幹線はそれぞれの沿線地域と同じ(山陽・九州は60Hz、東北・上越は50Hz)。
いずれの電気方式においても、変電所間での位相(北陸新幹線においては周波数)の相違を解決する必要があるが、高速を維持するため連続力行運転を行うことから、変電所の饋電区間の境界は、在来線のようにデッドセクション(アーク発生防止のため惰行で通過する)ではなく、地上切替方式を採用している。
切替区間はエアーセクションで区分され、その前後の変電所の双方から饋電でき、最初は進入側の変電所から饋電し、列車が切替区間に入ったことを検知すると進出側の変電所からの饋電に切り替える。
この間はおよそ0.5秒程度であり、乗客が切替を感知することはほとんどない。
ミニ新幹線である山形新幹線と秋田新幹線は、改軌前より50Hz・20,000V交流電化された区間であったため、改軌後もこれをそのまま採用し、直通車両を複数電源対応とした。
この場合の異電圧区間の接続はデッドセクションとなっている。